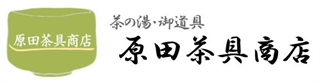入門の道具
-
茶道に入門するとまず基本となる所作を学びます。戸の開け方や扇子を用いての挨拶の仕方、畳の歩き方などの基本となる動作です。次に、帛紗を用いてのふくささばきを教わります。これらの動作は初めは頭で考えて動くため、ぎこちなくなりますが数をこなす事により自然と身体が動くようになります。焦らずゆっくりと身に付けていくと良いです。次に、お菓子を頂きお茶をのむ客の所作へと進んでいきます。ここでは入門してまず必要になる道具のご紹介をさせて頂きます。
-
帛紗(ふくさ)
棗や茶入、茶杓を清めるのに使います。男性は紫色。女性は表千家では朱色、裏千家では朱・赤の他、柄入の友禅やカラーも使えます。大きさは同じだが号数や匁によって分厚さが異なり、表千家ではちり打(音をポンと鳴らす)を行うため厚めの物を用いる。正絹と人絹の物があるが正絹の方が圧倒的に捌きやすく、上達に大きく関わってくる。その他、諸流派においては専用の柄や大きな寸法の物もある。
-
-
扇子(せんす)
挨拶をするときや自分の座る位置の後ろに置いたりする。流派によって細かな決まりがある。例えば、表千家は6.5寸黒染・黄骨が決まりである(写真の物)裏千家は女性は5寸、男性は6寸。諸流派によっては既製品がない物もある。茶室で開く事はないです。
-
-
懐紙(かいし)
お菓子を頂く時にのせる紙のこと。菓子器で出されたお菓子を取り分けて戴きます。夏季の水菓子にはりゅうさん紙を挟んだり、ラミネート加工された物を使います。また、紙を押し上げた「浮彫」や絵が印刷された「カラー」、すかしを入れた「透かし」などのデザインが施されたものもある。
-
-
楊枝(ようじ)
お菓子を食べるのに用います。黒文字や竹の楊枝もあるが、これらは亭主から出されたり、御稽古に忘れた人の為に出される事も多いので、所持品としては扱いやすいステンレスが望ましい。
-

-
懐紙入・帛紗挟(かいしいれ・ふくさはさみ)
上記の道具をまとめて入れる袋。大き目の「数寄屋袋」やコンパクトな「三ツ折」や「つづれ」などの種類がある。数寄屋袋は帛紗が四つ折で入るが小さい物は八つ折になる。また、数寄屋袋は茶会の時などに貴重品を入れ易く、三ツ折やつづれはコンパクトで持ち運びやすいのが特徴。
-
-
以上が御稽古に必要な物です。
濃茶点前に進むのに、「出帛紗」(表千家など)や「古帛紗」(裏千家)などが必要になっていきます。
裏千家さんなどは濃茶の飲み口を清めるのに「紙小茶巾」や「小茶巾挟」も用意をされます。
これらが、入門者が揃える物の一式となります。